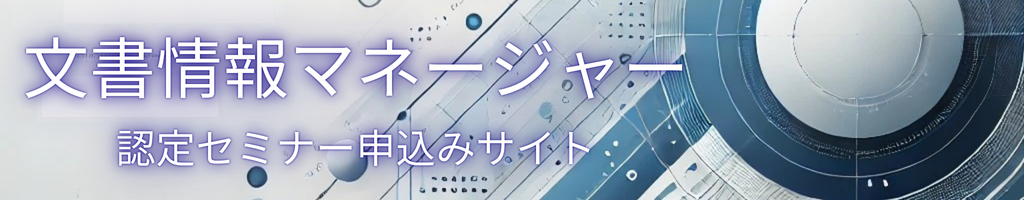エストニアでは、中高生が「バックアップの重要性」も学んでいる ― 教育の違いが、公文書管理の実力差を生む ―
▶はじめに
「電子決裁文書はPDFで保存したから大丈夫」
「クラウドに置いてあるから安心」
日本の自治体現場では、こうした声が少なくありません。
でも実際には、
- 誰がいつ改ざんしても分からない構造ではないか?
- バックアップは取得されていても、検証されているか?
といった問いが投げかけられたとき、答えに詰まるケースが多いのではないですか。 では、どうすれば“文書をきちんと管理する力”を持てるのでしょうか?
そのヒントが、IT立国と言われるエストニアの教育制度にあります。

▶ エストニアでは、文書管理の“基礎”を中高生が学んでいる
エストニアでは、国としてデジタル社会を築く方針のもと、初等・中等教育段階から「情報リテラシー(Digital Competency)」の育成に力を入れています。
中学校(Basic School)から高校(Upper Secondary School)にかけて、ICT(情報と通信技術)という科目が必修とされ、以下のような内容が一貫して教えられています。
- データの保存と構造化:記録の整理・分類の基本
- クラウドサービスの利用:共有・管理の仕組みを理解
- バックアップの必要性と方法:消失リスクへの備え
- ファイルのバージョン管理:履歴の可視化・改ざん防止
- セキュリティとリスクの理解:安全性と真正性の確保
これらは、公文書管理やアーカイブの現場で必要とされる知識そのものです。つまりエストニアでは、「記録を残す力」が、日常的な教養として育まれているのです。
▶ さらに、大学では「公文書管理」を専門的に学ぶ
タリン大学やタルトゥ大学では、公文書管理(Records Management)やアーカイブ学のカリキュラムが整備されており、地方自治体や政府機関で働く職員が、理論と実務を体系的に学ぶ環境が整っています。
教育が土台にあるからこそ、システムの導入だけでなく、「どの情報を、なぜ、どのように残すのか」という判断が、現場でできる人材が育つのです。
▶ 一方、日本では…
日本ではICT教育の必修化はようやく始まったばかり。 文書管理や記録保存の基本は、「現場に配属されてから自力で学ぶもの」とされがちです。
その結果、
- システムは入っているが運用が定まらない
- 電子決裁文書の保存ルールが組織で共有されていない
- バックアップが不十分な状態
といった“見えない不安”が自治体内に蓄積しているのが現状です。
■ だからこそ、このJIIMAのセミナーで「基礎」から学びましょう
(1)文書情報マネージャー認定セミナー
・文書情報マネジメントの基本から応用まで
(2)自治体向け公文書管理セミナー
・自治体の公文書管理に特化した文書情報マネジメント 文書管理の重要点は、ITツールの使い方ではありません。
「信頼できる記録を残す」ための判断力と考え方を、今こそ学ぶ必要があるのです。 教育を受けてこなかったことは、あなたの責任ではありません。 しかし、学ぶ機会を利用するかどうかは、あなたの判断です。
ぜひ、この二つのセミナーで、公文書管理の“基礎体力”を身につけましょう。