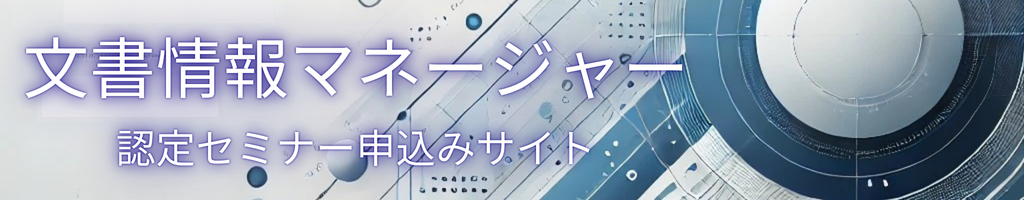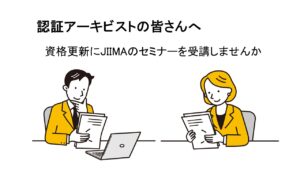LTO10登場、30TB/巻! 下位互換性なし、時代に求められる“新たな長期保存のしかた”
▶LTO10登場、30TB/巻!
2025年6月、ついにLTO(Linear Tape-Open)の第10世代が登場しました。非圧縮で30TB、圧縮時には最大75TBという大容量は、テープストレージの新たな到達点を示しています。これにより、大量データのバックアップやアーカイブ用途において、より少ない本数での管理や、保存スペースの削減といったメリットが期待されます。

▶ これまでの互換性の仕組みが見直された
従来、LTO規格では「2世代前までの読み取り互換」「1世代前の書き込み互換」が可能という仕様が採用されており、世代をまたいだメディア運用が比較的容易でした(この互換性モデルはLTO7まで適用されていました)。
しかし、LTO8以降はその互換性が段階的に縮小され、LTO10ではLTO9を含む過去のメディアを読み取ることができない設計となっています。これはLTO規格としては初めて、従来世代との互換性が完全に提供されない構成であり、運用戦略の見直しを求める転機と言えるでしょう。
▶データの保存には、計画的な「移行」が不可欠
これまでLTOシリーズでは、最新世代のドライブでも前世代のメディアを読み取ることができる「互換性」が前提となっており、これにより世代をまたぐ保存と運用が可能でした。しかし、LTO10ではこの互換性がなくなったため、過去のメディアを新世代ドライブで直接読み出すことができなくなっています。
長期保存用途では以前から、旧世代のメディアを新世代のメディアに定期的に書き直していく運用が求められてきました。特に、保存しておきたい期間が機器の供給・保守期間を超えることも少なくなく、「保存しておきたい期間 > 機器供給・保守期間」という構造的な課題は常に存在しています。
今回のLTO10登場を機に、この「移行の仕組み」をあらためて見直す必要があるといえるでしょう。
▶新たな長期保存のしかたとは
今後の長期保存戦略では、以下のような見直しが考えたいところです。
- 媒体とドライブの「セット運用」 古いメディアを保存するだけでなく、それを読み出せるドライブも一緒に保有し、運用管理する必要があります。
- 橋渡し世代での段階移行 LTO8→LTO9、LTO9→LTO10のように、互換性があるうちに段階的にコピー移行しておくことが、今後のベストプラクティスになります。
- 媒体更新スケジュールの設計 媒体寿命に頼るのではなく、5年~10年ごとに次世代媒体へ定期移行する計画を組み込みましょう。
▶最後に
LTO10の登場は、テープストレージが今も進化を続けていることを明確に示しました。一方で、互換性の見直しという仕様変更は、私たちのデータの長期利用戦略にも大きな転換を迫ります。テープは確かに強力な長期保存用の媒体ですが、「運用設計」次第で、資産にもなりまずが、負債にもなり得ます。
「読める状態で保存する」という基本に立ち戻って、長期保存の仕組みを見直してみるタイミングかもしれません。
このような考え方の基礎を学ぶにはどうしたらよいか。──ぜひ、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)の提供する「文書情報マネージャー認定セミナー」を受講しませんか。