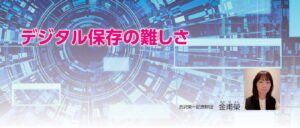リコージャパンが語る文書情報管理士の重要性とその背景

※この記事は、機関誌IM2024年11・12月号の再掲記事となります。掲載当時の情報に基づいているため、現在の状況や制度、取り組み内容と一部異なる場合があります。
最新号はこちら。
文書情報管理士検定団体受験 企業インタビュー
文書情報管理士の資格を社内の推奨資格としているリコージャパン株式会社では、検定試験が行われる夏と冬の年2回、あわせて100名以上の方が資格取得を目指してこれまで5年以上にわたり団体受験という形で申し込みをされています。企業として文書情報管理士を推奨資格としているその理由と、社員個人にもどういったメリットがあるのか、インタビューにて伺いました。
(取材日 2024年8月30日)
インタビュアー
JIIMA文書情報管理士検定試験委員会 担当理事 廣岡 潤
進行役
JIIMA広報委員会 担当理事 河村 武敏
インタビュー リコージャパン株式会社
デジタルサービス企画本部 EDW企画センター EDW戦略室 コンテンツマネジメント企画グループ リーダー 川上 宣久 氏
デジタルサービス企画本部 EDW企画センター EDW戦略室 コンテンツマネジメント企画グループ 寺井 利央 氏
デジタルサービス技術本部 DSPSソリューション事業部 第一ソリューションデリバリー部 技術2グループ 奥村 彰太郎 氏
人事・コーポレート本部 人事センター プロ化推進部 プロ化企画グループ リーダー 小林 勝也 氏
デジタルサービス企画本部 EDW企画センター EDW事業推進室 事業推進グループ リーダー 隅谷 寛人 氏
JIIMAにおける今後の文書情報管理とは
廣岡 1967年に始まったマイクロ写真士は、時代の変遷を経て2001年に文書情報管理士に名称が変更され、これまで累計で1万8千名を越える方が認定されています。この間、紙中心だった文書情報は、データで発生した文書情報がそのままで組織の垣根を越えて利用される「文書情報流通」という状態に環境が大きく変化しました。JIIMAでは今年5月に発表したJIIMAビジョンで掲げている「DXを加速させる」の実現には、安全な文書情報流通を実現させるための適切な文書情報マネジメントが重要であり、それを実践する正しい知識を持った文書情報管理士を育成することが必要であると考えております。このため指定参考書である「文書情報マネジメント概論」の新版を2025年3月に発行する予定です。本日お伺いしたことを改訂作業にフィードバックさせていきたいと考えております。

推奨資格になった理由とその効果とは
河村 文書情報管理士の上級から文書情報マネージャーという資格をお持ちの方にも本日のインタビューに参加いただいていますが、これら資格を取得するきっかけがあれば教えていただけますか。
川上 リコーは複合機を中心に展開しているメーカーですが、現在はお客さまの文書管理からその利活用などドキュメントソリューションを含めた総合的な提案を行っています。私が所属するコンテンツマネジメント企画グループは、基本的に文書管理ソリューションやクラウドストレージ製品を取り扱っております。業務を行う上で、文書管理の重要性が増し、JIIMAの「文書情報管理士」という資格が役に立つということを知って、推奨資格としました。資格取得することによって、社員の人事評価のレベルアップやモチベーションアップにもつながっています。

廣岡 御社からは管理士の団体受験の申し込みが定期的に行われておりますが、「文書情報管理士」が推奨資格になったのは具体的に何か理由がおありでしょうか。
川上 紙をデジタル化して運用するだけではなく、現在はデータtoデータが主流となってきており、その中でワークフローを構築するソリューションも増えています。これらの知識やスキルを身につけて、お客様にDX(デジタルトランスフォーメーション)の提案をするためには、言葉だけではなく目に見える資格も重要になってきます。
寺井 そもそもリコージャパン社内では「プロフェッショナル認定制度」(以下、「プロ認定制度」)という仕組みがあり、個人のスキルやノウハウが評価される制度に人事システムが変更されました。いろいろなソリューションがあり、いろいろな分野がある中で、その分野ごとにいわゆるマスター級とか1級2級などランクが分けられていて、その中でそれぞれのランクに到達するためにはこういった資格を持っていなければいけないという体系を作ろうとしたわけです。当初は、このプロ認定制度の仕組みに文書情報管理士は入っていませんでした。ただ、このプロ認定制度の枠組みがどんどん大きくなるにしたがって、さらに細分化された資格が必要ということになり、その際に話にあがったのが文書情報管理士です。特にその中で文書情報管理士の上級資格を取得できれば、ドキュメントソリューションの分野を担当する社員としてはこれが最上位に位置づけたらよいのではないのかとなり、文書情報管理士をドキュメントソリューション分野の上級資格として位置づけたという経緯があります。
廣岡 団体受験の申し込みはその流れでということでしょうか。
寺井 そうですね。今後のプロ認定制度が新しい制度体系で進むと決まった際に、社内で文書情報管理士の受験者を募集した所、かなりの人数が集まりまして、そんな中、JIIMAから「団体受験で申し込まれたほうが受験料の割引があります」という話を聞いて、それならば定期的に団体受験で申し込むスキームを作ったほうがよいということになり、今も定期的に団体受験で申し込みさせていただいています。
小林 プロ認定制度の関わりで文書情報管理士の資格を取得するのは、当初は「コーディネートセールス」と呼ばれる複合機周辺のソリューションを提案する営業やシステムエンジニアが主体でした。その後、スタッフ職の方々も資格を取得していく流れになり、電子帳簿保存法の関係もあって、さらに約2,000名が資格取得の対象に加わりました。結果的に7,400名ぐらいの方々にとって、この資格を取ることがプロ認定制度のレベルアップ要件になってきている、という状況です。リコージャパンでは自らがソリューションを使い、その社内実践を事例とし、営業はもちろんエンジニアもスタッフも、その実践と資格を活かし、お客様に有効な形で提案するということを意識しています。社内に文書情報管理士という資格を有するメンバーがどの分野にも大勢いることは、お客様への提案や社内業務の上で大きなメリットとなっています。
社内の資格取得の状況について
廣岡 文書情報管理士以外にその他の推奨資格は、例えばどのようなものがあるのでしょうか。
小林 現在は約800種類あります。例えば、ビジネス・キャリア検定などは、人事や経理、営業・マーケティングなど細かく分かれていますが、当社では職種細目が80種類に分かれていまして、それら80種類の業務にあわせてどの資格が必要なのかという建付けをして、スキルマップみたいなものができあがっています。
廣岡 推奨資格が800種類もあるっていうのはちょっと驚きですが、御社の中での文書情報管理士の認知度はいかがなものでしょうか。
小林 先ほど説明させていただいたコーディネートセールスをする対象メンバーが2,000名、システムエンジニアとしてそれらを構築するメンバーも同じように1,400名、スタッフ職は4,000名くらいが対象となっています。プロ認定制度は社員14,000名が対象ですから、おそらく半数の7,000名以上の方は文書情報管理士の資格を取らないといけないと認識しているのではないかと思いますね。
河村 驚きました。御社からは毎年何名くらいの方が文書情報管理士の団体受験に申し込みいただいているのでしょうか。
小林 夏と冬で合計100名から140名前後、現在ではトータルで550名ほどが社内で文書情報管理士の資格を持っています。ただプロ認定制度が始まってまだあまり時間が経ってない職種もあります。営業やシステムエンジニアはすでに多くの社員が取得していて、スタッフ職は一昨年から対象となったので、今後はスタッフがどんどん受験していく形になると思います。

資格へのチャレンジ精神を養う社内環境
廣岡 合否判定する立場で見ていますと、御社の受験者数が多いというのも驚くべきことなんですが、それ以上に御社の受験者の成績が非常に良いと感じております。これは何かしら社内の勉強会があるかと想像していたのですが、そういった教育制度的なものは何かございますか。
小林 もともと社内でプロ認定制度が始まる前から、毎週水曜日の業務開始1時間は学習する時間にしていいという仕組みがありました。そういった時間を有効活用して学習しているのが一つ、あとは、資格を取るための支援制度を設けています。全社員を対象に、1年間に何資格まで支援しますよ、というような形になっていますので、そういった会社からの支援なども活用して、みんなチャレンジをしてくれているんじゃないかなと思います。
廣岡 支援というのは具体的には、受験費用や参考書の費用とかそういったことですか。
川上 その通りです。
廣岡 資格取得できると先ほどプロ認定制度のレベルが上がると伺いましたけど、給与の面で資格の手当てや、あとは人事評価的なところにも何か連動するようなものがあるのでしょうか。
小林 連動しています。プロ認定制度というのは、プロレベルが8段階あります。一定レベル以上になると手当てがまず出ますよ、という制度になっています。その手当てが出ることにプラスして、一定レベル以上になると自分の処遇が上がるようなシステムになっています。すべての社員が必ずなれるわけではありませんが、それに紐づいてある一定の成果・行動を伴っている社員というのは、処遇が課長相当まで上がる形になっています。プロレベルが上がることが、自分の待遇や処遇が良くなるというところにつながっているというシステムになってはいます。
廣岡 なるほどよくできていますね。政府のほうでもよく「リスキリング※1」という言葉を使っていますが、御社は先行して制度化されていたのでしょうか。
小林 そうですね。そういうリスキリングと言い出したタイミングと、全社員でがんばろうねというタイミングがぴったりあった部分はありますね。
川上 プロ認定制度の知識という分野では、外部資格を取得することでポイントを得られます。例えば文書情報管理士1級だと5ポイントとかそういうポイント付けがあるので、どの試験にチャレンジしようか、社員は各自考えています。先ほど、社内の勉強会の時間、そして金銭的支援の話がありましたけど、部署内で例えば文書情報管理士の1級など上級の資格を持っている人が講師役になって、資格受験対策の勉強会も実施しています。これは文書情報管理士だけにかかわらず、マーケティング研究やビジネス・キャリア研究とか勉強会にはいろいろな種類があります。
寺井 補足になりますが、勉強会ではどんなふうに勉強をしたのかとか、どれくらい時間をかけたのかといった体験談などを、水曜日の朝1時間で発表しています。最初は、会社で勉強なんて面倒だと思っていた社員もいたと思いますが、最近ではみな勉強会に対してより自発的になってきて会社全体の体質そのものがいい方向に変わってきています。
廣岡 社員全員がスキルアップすることで会社全体の質が上がっているという感じですね。水曜日の朝1時間は他にどんな勉強をされているのでしょうか。
川上 基本的に水曜の勉強時間は朝9時から10時までです。最近は外部試験の勉強会の他にも、自社の商品知識向上の勉強会をやったり、社外のパートナー企業から講師を招いてセミナーを開いてもらったり、社内整備しているe-Learningのデジタルコンテンツでの勉強などいろいろな手法の勉強会を行っています。ちなみに勉強会はリコージャパン全社員約18,000人が対象になっていまして、テレワークの社員も多いので、リモートで勉強会に参加することも可能となっています。
※1 リスキリング 技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶこと
名刺記載は営業の武器。官公庁入札での必須資格
河村 では次に視点を変えまして、社員のスキルとしての文書情報管理士としてではなく、お客様への対応としての文書情報管理士の資格はどのように活用されておりますでしょうか。
奥村 私が文書情報管理士2級の資格を最初に取ったのは2017年でした。その半年後に1級に合格しまして、2019年には上級の資格を取得しました。更新手続きもちょうど先月行っています。名刺にも「文書情報管理士 上級」という文言を入れさせていただいているのですが、実感としてこの資格に対して反応がよいのは官公庁関連です。
廣岡 入札参加資格に必要だからですね。
奥村 そうです。入札参加資格のところにファイリングデザイナー2級または公文書管理または文書情報管理士1級以上というものがちゃんと明記されていましたので、資格の取得が役に立ちました。
河村 なるほど。
奥村 民間企業ではまだまだピンとくるとかはないのかもしれませんが、私の職務上、文書管理ドキュメントソリューションを担当しているので、訪問先で名刺を見せた際、文書管理の相談ができるんだなと分かっていただけるみたいで、雑談から始まって別の部署を紹介していただいたり、文書管理で困っているという相談を受けることはよくあります。
河村 奥村さんは文書情報管理士以外にも「文書情報マネージャー」認定の資格もお持ちなんですね。

奥村 はい。そちらも受講しまして、JIIMAで実施している資格はすべて取得させていただいています。またJIIMAの資格ということで、現在、電子帳簿保存法関連でJIIMAというキーワードは一般にもかなり浸透してきています。弊社の製品もJIIMA認証を受けておりますが、JIIMA認証を担保している資格ということで、文書情報管理士の有用性を感じています。
河村 文書情報管理士と文書情報マネージャー、この資格の信頼性、そして営業での貢献度が高かったということでしょうか。
奥村 そうですね。とくにJIIMA認証からJIIMAという団体を知っておられる方も多いので助かっていますね。
廣岡 電帳法関連は我々JIIMAとしてはずっと昔からやっていたことがやっと花開いたというところでして、電帳法以外の部分もJIIMAとして強化していきたいと感じてはいます。
川上 やはり電帳法におけるJIIMA認証は大きいですね。官公庁など大手を取り扱っている営業支援だけじゃなくて、中小企業の担当もJIIMA認証という言葉は知っておられます。さらにもっとJIIMAの知名度が広がっていただければ、名刺に文書情報管理士の資格を記載しているメンバーも非常に助かると思います。
廣岡 ご指摘ありがとうございます。リコージャパン様の立場や目線からいろいろとご指摘いただけることはありがたいです。
河村 電帳法の宥恕期間も去年の12月で終了しましたが、それでも中小企業などは対応が進んでいないところもあると思います。それら企業を対象にしたビジネスチャンスはまだまだあると考えられますので、JIIMAとしてもJIIMA認証を取得されている企業様をさらに支援していければと思っています。

教育制度について今後の展望と文書情報管理士に求めるもの
廣岡 これまで御社の教育制度をいろいろとお話聞かせていただきましたが、教育制度について今後どのように発展させるご予定なのかを教えていただけますでしょうか。
小林 現在、少子化の波が我々にもあって、社員一人一人が複数のスキルを有して生産性を高める必要を感じています。今までですと、例えば営業でも複合機周辺商材の専門といったように専門領域がありましたが、今ではICTなどについても複数のスキルが求められるようになっています。複数のスキルを持つスタッフがいろいろな役割を担えるような形にしていきたいと思っていますので、社員みんなでさまざまな資格にはチャレンジしてほしいな、というふうに考えています。
廣岡 少子化に向けての準備ということですね。
小林 ただそうは言っても、その資格の知識が時代にあわせてアップデートされていかないと意味がありませんので、古いスキルではなく新しいスキルを有してほしいというふうに思っています。
廣岡 厳しい話ですがまったくその通りですね。
小林 お客様へ最適なソリューションを提案するには、社員には常に新しいものをチャレンジしてもらうように働きかけていって、社員全員が各種の資格を有してお客様にいろんな提案ができるようにしていきたいと考えています。
廣岡 文書情報管理士もアップデートを図ろうと教科書改版作業を進めておりますが、改めまして文書情報管理士の資格制度自体に求めたいというところは何かございますでしょうか。
小林 資格については繰り返しになりますが、新しい情報が学べるようにしてほしいというところですね。プロ認定制度は毎年推奨資格の見直しをしておりまして、文書情報管理士においても常に時代にあわせた最新スキルが学べる資格であってほしいです。
河村 コロナ禍以降、DXという言葉が広く一般に使われるようになりましたが、DXに関する検定なども取り入れているんでしょうか。
小林 800資格の中にDX検定自体も含まれています。特にリコーグループ全体でITSS(ITスキル標準)のレベル3から5ぐらいの資格にチャレンジしましょうという目標を持っています。あとはデータの取り扱い、データを変換してどう分析するかがこれから重要になってくるので、情報IPA関連の資格も順次増やしていってます。
河村 資格にチャレンジする方が社員全体で増えてきているということでしょうか。
寺井 増えてきています。特に最近では情報セキュリティ関係が一番多いですね。もちろん自分の業務の役割やミッションとか、仕事に関連する資格をまず選んだ上で取得を目指すという基本ありきではありますが。

JIIMAへの要望とは
廣岡 最後になりますが、我々JIIMAの活動について会員企業であるリコージャパン様の視点から何かご希望があったら伺いたいのですが、いかがでしょうか。
寺井 資格試験や認証制度などいろいろやっていただいておりますが、特に政府や行政機関とかそういったところに対する政策提言をより行ってほしいです。電帳法に関する規制緩和もそうですが、企業側としてはよりお客様に提案しやすいように、お客様に対しても法律を柔軟に運用できるように、ご配慮いただいけるような形でぜひ意見を発信していただければと思います。
(敬称略)